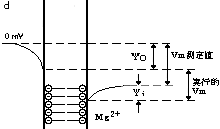神経とカルシウム
小倉明彦:大阪大学大学院理学研究科 : 生物科学専攻
1)血液脳関門
私が子どものころ、グルタミン酸が脳内の情報伝達に重要な働きをしているという慶応大学の林髞教授の発見が報じられたとき、『だから、グルタミン酸を飲めば頭が良くなる』という噂が飛んで、それを信じた母から毎日小さじ1杯ずつの味の素(ほぼ純粋なグルタミン酸のナトリウム塩)を飲まされた経験がある。
さっぱり成績が上がらなかったからか、いつの間にかやめになってくれて助かったが、生理学的にいってこの噂には無理があった。からだには体内の環境を一定に保つための機構が備わっており、何かを食べたからといってそれがからだの成分に直接取り込まれたりはしないのである。魚を食べると泳ぎがうまくなるとか、虎を食べたら勇猛になったとかいう話はおとぎ話の世界に限られる。
、血液中にすらなかなか入らないうえに、中枢神経組織には血液脳関門と呼ばれる特に厳重なバリアーが設けられている。医薬にしても静脈注射や、まして経口投与によって中枢神経細胞に届くように設計することは容易なことではない。
血液脳関門について簡単に説明しよう。脳は神経細胞だけからなる組織ではない。神経細胞を上回る数のグリア細胞があって、神経細胞の電気的絶縁や侵入した異物の排除、髄液の撹拌・輸送に携わっている。上に述べたバリアーもグリア細胞(アストログリア細胞)の機能の一つである。グリア細胞が神経細胞と血管細胞の間に立ち、グリア細胞の細胞中に取り込まれくぐり抜けた物質だけが脳神経細胞に届くという仕組みになっており、この検疫所のような機能が血液脳関門である。
したがって、以下で神経組織でのカルシウムの重要な役割について順に説明していくが、『ではカルシウムをたくさん食べればいい』というふうには短絡しないでいただきたい。もちろんカルシウムを摂取することは健康維持に重要で、牛乳はカルシウムを豊富に含む食品として大変有用な飲料ではあるけれど、飲んだカルシウムが全部そのまま血液に反映して血中カルシウム濃度が敏感に刻一刻変動するわけでもないし、飲んだ牛乳中のカルシウムが直接脳細胞に届くわけでもない。
2)血液と脳脊髄液の組成
中枢神経細胞をとりまいているのは脳脊髄液(髄液)という組織液である。主な無機質組成を表1に示した。 髄液は脳内で脈絡叢上皮細胞が血液を濾過してつくる。これも血液成分が直接脳神経細胞に触れることがないように設けたバリアーの一つである(血液髄液関門という)。 例えばナトリウムイオン(Na+)濃度やカリウムイオン(K+)濃度はほとんど等しいなど、血液(血清)の成分比を一定程度反映しているのは事実だが、カルシウムイオン(Ca2+)濃度は血漿中濃度の約60%で決して等しくはなく、濃度を別に調節している機構が脈絡叢にあることを示している。 |
【表1】血液(血清)、リンパ液(組織液)、髄液(脳脊髄液)中の主なイオンの組成比較
( 単位 mM )日本生化学会編、生化学データーブック、東京化学同人(1979)より抜粋 |
他章で説明されているように、血漿中Ca2+濃度自体が巧妙な濃度調節機構で制御されているうえに、もう一段調節機構があって髄液中濃度を注意深く一定に保っているという事実は、逆にCa2+が神経活動に大きな影響を及ぼすことを暗示している。
1)電荷を運ぶ実体として 神経細胞に限らず細胞は一般に内外に電位差をつくっている。神経細胞の場合、通常内側が外側に対して60〜80mV負に帯電(分極)している(図1-aのVm)。 脱分極が脱分極の連鎖反応を引き起こすのは、電位依存性イオンチャネルと呼ばれる分子が細胞膜中にあるためである。 これらのイオンは、後述の機構を使って、常に細胞内の濃度が細胞外より低くなるように維持されている(ヒトの脳が、重量は体重の1/30程度でありながら、全エネルギーの1/3程度を消費する”贅沢な ”器官なのは、このイオン汲み出しのためである)から、扉が開くとどっと細胞内に流れ込む。 Naチャネルは神経細胞では軸索と呼ばれる細長い細胞突起(これが何百本も集まって銀白色の束になったものが、私たちが鶏肉などで肉眼で見ることができ、運動神経とか感覚神経とか呼んでいる神経である)のうえに主に存在する。 Caチャネルの方は軸索末端と呼ばれる次の神経細胞との接続部分に主に存在する。そのことの意義については(3−1)で再び触れる。 |
【図1】カルシウムによる鎮静効果(遮蔽効果) a:細胞膜に電荷がないと仮定した場合。 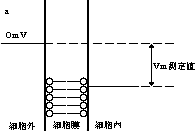 b:実際には細胞膜の内外表面に負の固定電荷があるため、膜の近傍の電位は負側に引き下げられる。 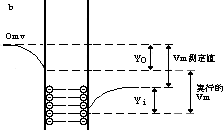 c:細胞内外の2価陽イオン膜の電荷が中和されると、引き下げ幅は小さくなる。 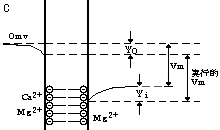 d:細胞外の2価陽イオンが不足すると、細胞外の引き下げ幅は再び大きくなる。 いずれの場合も、細胞膜から離れた位置に電極を置いて測定されるVm測定値には差がないが、イオンチャネルを含む膜蛋白が感受している膜の直内直外の電位差(実効的Vm)に差が生じる。dでは実効的Vmの減少、つまり脱分極と同等になっている。 |
2)鎮静物質として(図1)
神経細胞の1カ所が興奮すると、その脱分極が隣接部位を脱分極させてそこを新たに興奮させる。花火の導火線は、端に点火すると、その発熱で隣接部位を発火させ、それがさらに隣を発火せることを繰り返しながら火を花火に届けるが、活動電位もそれと似た方法で軸索を伝わっていく。だから、神経が興奮するかしないかの出発点は最初の脱分極である。これをしばらく憶えておいていただきたい。
細胞膜はリン脂質の二重層でできている。リン脂質の成分の多くは一端にリン酸基に由来する負の電荷をもっているから、細胞膜は全体として内外の表面に負電荷をまぶしたシートのようなものを想像して下さればよい。すると、細胞膜の表面近くは遠くより電位が低くなっており(表面電荷:図1−bのΨi、Ψo)この付近の電位プロフィールは、VmにΨが加わった形になっている。ただし細胞内外にはCa2+やMg2+があるから、通常そのΨi、Ψoの一部分は中和されている(図1−c)。これを2価イオンの遮蔽効果と呼ぶ。このようにして最終的につくられたVm'が細胞膜に実際にかかっている電位差ということになる。
さて、何らかの理由で細胞外のCa2+濃度が下がってしまったとしよう。すると細胞外のΨoを中和できなくなるから、図1-dのようなプロフィールになる。このとき問題のVm'は、中和があったとき(図1−c)に比べて小さい。これは脱分極したのと同じことである。このような理由で、細胞に針を刺して測定される『沖の方』の電位Vmには変わりなくても、細胞膜に実際にかかっている電位差Vm'は脱分極状態にあることになる。さきほど憶えた点を思い出していただければ、細胞外のCa2+濃度、Mg2+濃度が下がると神経細胞が興奮しやすくなることが推論されるだろう。医師仲間の会話で(あるいは普通の日常会話で)、プリプリ怒りっぽい人を『カルシウム不足だ』とからかうが、これにはこういう複雑な背景がある。
1-1),2)で述べた血液脳関門や血液髄液関門は、中枢神経系(脳と脊髄)に備わった第二段目の恒常性維持機構である。これに対して、末梢神経系は基本的に血漿と等価な組織液に浸っている。だから確かに、第一段目の恒常性維持機構である血漿中のCa2+濃度調節機構が崩れてこれが下がると、運動神経や骨格筋の興奮(けいれん)が起こりやすくなる。これが、例えば呼吸停止で血中HCO3−濃度が急上昇した場合などに起こる低カルシウム血症の症状である。しかし、中枢神経系細胞が興奮しやすくなるのは恒常性維持装置が二段とも機能しなくなった場合に限られるから、自分が上司にいつも叱られるのは上司のカルシウム不足のせいではなく、やはり自分に非があると考えた方がよい。
3)細胞接着補助因子として(図1)
体内のほとんどの細胞は、組織液中にバラバラに浮かんでいるわけではなく、同種の細胞どうしまたは特定の異種の細胞どうしが、細胞接着分子と呼ばれる一群の分子を介して互いに接着している。その中にはCa2+の存在を機能上必要とする分子も多い。カドへリンと呼ばれる分子もその一つで、神経細胞の機能、特に発生初期に神経細胞が連絡網をつくり上げていく際に重要な働きをする。
カドへリンは細胞膜を貫通して内外に顔を出している蛋白質で、外側に出た部分で隣の細胞が出しているカドへリンと結合し、内側の部分でカテニンなどの蛋白質を介して細胞骨格(3−3)参照)と結合する。カドへリンには幾種類もの亜型があり、それぞれが同型のカドへリンと結合するので、細胞が時期によって合成するカドへリンの型を変えれば、それに応じて細胞集団は集合したり離散したりできる。そしてまさにそういうことが神経系の発生時に起きている。
卵が受精して発生をはじめ袋状になると、やがて外側の層の一部がくびれ込んで管をつくる。これが中枢神経系の起源で、このとき管をつくる細胞群はカドへリンNを合成し、くびれ込まずに外側に残って将来皮膚になる細胞群はカドへリンEを合成している。というより、この時期に外層中の一群の細胞がNを合成するように変わる結果、Eを合成している細胞群から離れざるをえず、Nどうし集まって管をつくることになる。このような接着と不接着を使い分けて器官・組織をつくり上げていくというシナリオは、動物の形態形成に普遍的な原理で、カドへリンはその中心役者の一人であるから、発生中に何らかの原因でCa2+が不足すると、正しい接着ができずに形態異常を生じる。
1)神経伝達物質の放出
細胞内でCa2+の果たす生理機能は多種多様である。そもそも生命の原点である卵は、精子との受精の瞬間、細胞内のCa2+濃度を高めて以後の発生をスタートさせる。そのほか筋細胞では収縮が、繊毛細胞では停止や逆転が、腺細胞ではホルモンの分泌がはじまる。神経細胞も例外ではない。神経の最も重要な役割である情報の伝達そのものが、Ca2+なしでは行われないのである。
この点をもう少し詳しく解説しよう。神経細胞から神経細胞への情報伝達は、2つの細胞の接点(シナプス)で化学物質の授受によって行われる。1つの神経細胞の軸索の末端まで活動電位(2−1)参照)が到達すると、末端内に多数蓄積されていた小さな(シナプス小胞という)がはじけ開いて、小胞内に含まれる化学物質(神経伝達物質といい、多くの種類がある)が細胞外に放出される。これを開口放出という。この開口放出がCa2+要求性である。放出された物質は、狭い間隔を拡散して、待ち構える次の細胞まで届き、その表面である受容体分子に捕らえられる。伝達物質と結合した受容体は構造を変え、再び電気信号を発生し、こうして細胞間の伝達が完了する。
開口放出についてさらに詳しくみていこう。軸索末端の細胞内に外からCa2+を引き入れる役割をするのは2−1)に登場した電位依存性Caチャネルである。この分子が末端まで到達した電気信号を検知して分子構造を変え、扉を開くようにCa2+の通過を許す。そもそも細胞は、ふだんエネルギーを大量に使って細胞内のCa2+濃度を細胞外に比べて1万分の1程度の極低濃度に抑えているから、いったんCa2+を通す扉が開くと、Ca2+がどっと流れ込み、1秒の1,000分の1以下の短時間のうちに、ふだんの10倍から100倍もの濃度に急上昇する。
伝達物質を含む小胞の膜には多種類の蛋白質が結合している。その一つにスネアという蛋白質があり、軸索終末の細胞膜にあるスネアとの間で、スナップという蛋白質を介して結合している。つまり小胞はフラフラ漂っているのではなく、蛋白質の架橋によって細胞膜の内側に接岸・係留されているのである。さらに小胞膜にはCa2+センサー蛋白質がある(はずである:シナプトタグミンという蛋白質がそれだという説が有力である)。
この状態でCa2+濃度が高まると、センサーが働き、やはり小胞膜にある膜融合誘導蛋白質(シナプトフィジンという蛋白質がそれだろうといわれている)の構造変化を誘発する。接岸していた小胞の膜と細胞膜とは、これをきっかけに物理的に融合し、中身の伝達物質がシナプスの間隔に放出される。
活動電位が軸索末端に到達してから放出まで、1,000分の1秒程度で完了する早業だが、ともかくCa2+の流入がないと現象が進まない。実際の脳の中でそのようなことはまず起こらないが、実験的にシナプス部分の髄液(または実験溶液)のCa2+濃度を下げてやるか、Caチャネル上でCa2+と競合するMg2+の濃度を高めてやると、神経伝達はたちまち遅くなり、停止してしまう。