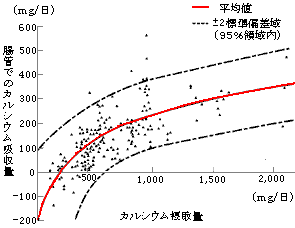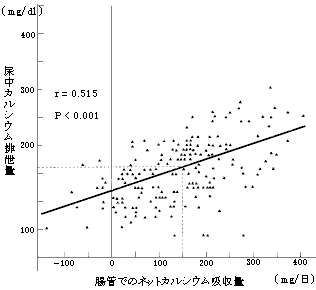カルシウムの不思議
西沢良記:大阪市立大学医学部第二内科
はじめに
カルシウム(Ca)は一つの元素である。元素の周期表(図1)でみると4週目にあり、カリウム(K)とスカンジウム(Sc)の間に位置し、周期表の2週目のベリリウム(Be)、3週目のマグネシウム(Mg)、5週目のストロンチウム(Sr)、6週目のバリウム(Ba)、ラジウム(Ra)が同じ2A属のアルカリ金属で、性格も似ている。原子量は40.08、質量数は40〜49で2個の正の電価をもつ。
、辞書でみると『天然に発見せられ、特に石灰の基礎的成分で、動植物の有機組織中に存在する重要元素』と記されている。この辞書で表現される【重要元素】という意味について考えることが、この章での目的である。
1.カルシウムって何?
カルシウムの生体での役割は、とても複雑で多岐にわたっている。例えばよくご存知の骨や歯を構成する主成分であるが、もっと機能的な役割をもっている。種々のホルモンの分泌やホルモンの作用発現、筋肉の収縮や弛緩、血液の線溶・凝固、消化管での消化・吸収、創傷の治癒、薬物作用の発現、無数に近い多くの酵素の作用発現、種々の受容体の作動、大多数の分子構造の形成・触媒・安定化、さらには植物の光化学機序の発現など生物が生きていくうえで必須の役割を担い、しかもカルシウムに代替できるミネラルはない。
、どうしてこんなに多くの役割を一つのミネラルに託しているのか不思議なくらいである。それほど、生体にとってカルシウムは重要といえよう。
2.カルシウムの栄養学での遍歴
ひと昔前は蛋白質が栄養素のトップブランドであり、食事や栄養の話になると『蛋白質は西欧人に比べて日本人に特に不足している栄養素』と考えられ、動物性蛋白質を摂ることが正しい食事のあり方であると納得していたことを記憶しておられる方も多いと思う。
、確かに昭和30年(1955年)では摂取エネルギーに占める蛋白質の割合は13.3%であった。現在では蛋白質の占める割合は15.6%で、所要量(40歳代女性55〜65g)の123%と増加している。
、脂肪摂取量の増加が健康生活の問題になるなど、蛋白質摂取増加で話題にもなるような時代になった。
最近、しばしばカルシウム摂取不足が栄養問題にあげられる。わが国では、摂取エネルギーや脂肪・蛋白質はもとより、ナトリウム、鉄などのミネラル、ビタミンなどは所要量を十分に充足できている。
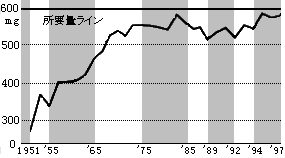 |
(図2)【カルシウム摂取量の年次推移】 全国平均1人当たりの1日摂取量 図2に1951年以降のカルシウム摂取量を示した。確かに現在でもカルシウムは必要所要量(年齢にもよるが600mg)を満たしておらず(579mg)、このために栄養の問題としてカルシウムがしばしば登場することになる。 |
しかし、よく考えると確かに不足していることはわかるが、90%以上充足しているのだから一般の感覚ではほぼ充足していることになるのではないかと反論したくなる。いつも100点満点をとらなくても90点以上もあれば十分ではないのですかといいたくなる。単に数字のゴロに惑わされているだけで、あと数%がそんなに大切なものとは実感できない。
この問題を実感してもらうためには、カルシウムをもっと知ってもらう必要がありそうだ。
3.カルシウムと地球環境
人間が住む地球の表層には多くの元素があるが、豊富な順番では、1番目は酸素、次いでケイ素、3番目が水素、そして、アルミニウム、ナトリウムとなり、6番目がカルシウム、さらに鉄、マグネシウム、カリウム、チタンの順番となる。地球表面にはカルシウムが豊富にあることがわかる。
、地球の表面を流れ、種々の物質を溶かしこんだ海水ではどうか。一番多いのは水素、2番目が酸素、3番目がナトリウム、4番目は塩素、そしてマグネシウム、イオウ、カリウム、8番目にカルシウム、さらに炭素、窒素となり、海水でもカルシウムは豊富に存在する。この海水の組成と地球上の生物の誕生とに壮大な物語がある。
地球上の動物には特別な特徴があることが知られている。地球上の動物は数えきれないくらいの種類がいるが、その生活環境が極端に異なっていても、一定の類似した水分含有量をもち、その体液のミネラル組成も濃度もほぼ共通している。この体液のミネラル濃度は約1%食塩水に相当する。まるで地球上の起源が同一で、環境による自然淘汰による選別・進化を受けてきただけでなはないかとさえ思える。
例えば、陸上に住む動物たち・・・・・・・水の豊富な熱帯雨林、比較的乾燥しているサバンナ、水分がほとんどない乾燥した砂漠に住む動物すべてにあてはまる。もちろん、ヒトの体液も生理食塩水の0.9%に相当し、例外ではない。3.7%の塩分濃度の現在の海水中に住む魚類、軟体動物なども、塩分を含まない淡水に住む魚類もほぼ同じミネラル組成の体液をもっている。
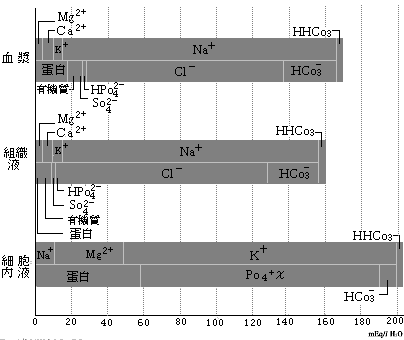 、体液のミネラル組成があらゆる動物に共通し、その濃度も海水の1/4に相当することから、1926年に生物学者であるマッカラムが有名な『 blood reflex the early seas(体液は太古の海を反映する)』学説を発表した。宇宙空間に地球ができたのが120億年前と考えられているが、40億年前には生物の祖先が海水中に生まれ、ある種類の生物(多分、古代の魚類)は海から河口をさかのぼり淡水に住むようになり、ある種は陸へあがって陸生(カエルやワニなどの古代の両生類や爬虫類)になったという説である。
、体液のミネラル組成があらゆる動物に共通し、その濃度も海水の1/4に相当することから、1926年に生物学者であるマッカラムが有名な『 blood reflex the early seas(体液は太古の海を反映する)』学説を発表した。宇宙空間に地球ができたのが120億年前と考えられているが、40億年前には生物の祖先が海水中に生まれ、ある種類の生物(多分、古代の魚類)は海から河口をさかのぼり淡水に住むようになり、ある種は陸へあがって陸生(カエルやワニなどの古代の両生類や爬虫類)になったという説である。、原始の生命体は海水と細胞膜で隔てた単細胞であったろうし、多細胞体になり、海水が体液の役割を果たして腸管のような栄養吸収器官や腎臓のような排泄器官をもつようになる。同時に鰓や肺などのガス交換器官など複雑な種々の器官ができ、心臓による体液の循環もできて、海から離れても自活が可能となり、体液としての成分が恒常的になってきたと考えられる。体液成分を図3に示す。
しかし、推定される太古の海のミネラル濃度は、マッカロンの仮定した濃度(食塩水でほぼ1%)ほどに低くはないとされている。表1、2に太古の海水のミネラル組成と現在の海水の組成を比較している。
|
【表1】 太古の海水と現在の海水のミネラル濃度の変遷 海水は時代とともに濃くなっているが、単細胞生物発生の先カンブリア期(40億年前)でも人体の体液濃度305mEq/リットルより2.5倍の高濃度であった。 オルドビス期(約5億年前)には脊椎動物の出現をみる(表中単位:mEq/リットル)。 |
|
【表2】 海水と体液のミネラル組成の比較 濃度は海水の方が3.7倍濃いが、ミネラルの比率は驚くほど類似している(表中単位:mEq/リットル)。 |
先カンブリア期は約40億年前の海水中に単細胞が発生した時代であるが、人体の体液ミネラル濃度の305mEq/リットルより2.5倍も高濃度である。オルドビス期は約5億年前で脊椎動物の出現した時代であり、人体の体液の3.2倍の高濃度で先カンブリア期の海よりさらに濃縮されている。現在の海水はさらに濃くて体液の約3.7倍になっている。
、海水は蒸発して雨となって陸に降り、陸地を川の水となって流れ、多くのミネラルを溶解した水が海水に注ぎ、長い歴史の結果として海水のミネラル濃度が増加してきたのであろう。しかし、古代の海水のミネラル濃度は体液より高濃度であり、マッカロンの説はそのままでは理解できず、若干の修正が1940年代にコンウェイらによりなされた。
、多分、淡水が流れ込む河口が酸素が豊富で、栄養や温度などの条件が良く、生物が発生しやすかったため。海水が希釈された低い濃度の海水中で繁殖し、この環境と同じ濃度の体液ミネラル組成ができあがったと推測されている。
4.カルシウムと体液調節
古代の海で生命体が誕生し、長い道のりを進化し続けてきた。単細胞生物から多細胞生物へ、古代の軟体生物から海生動物へ、無脊椎魚類から脊椎魚類へ、そして陸生動物の出現となる。この海中生活環境から陸上生活環境への順応にはいくつかの大きな進化が必要であった。
ひの一つは水中に溶けた酸素を摂取していた鰓から、空気より酸素を得る肺が必要となり、水中では浮力により軽かった体重が空気中では重い体重となるため、これを支える堅牢な骨格とより強力な筋力が必要となった。幸い、酸素は空気中に豊富に存在していたので生物は海の生活と大きくは変化しないですんだが、骨格と筋力は多種多様に進化し、多くの動物へと枝分かれして発達した。
環境変化により食物の摂取も激変する。海水中には多くのプランクトンのような食用微生物がいるが、陸生動物は呼吸するだけでは栄養が手に入らない。特に海水は3〜4%のミネラル水なのでミネラル摂取は魚類にとってはごく容易であり、むしろ摂取過多となる危険があった。ナトリウムやカルシウムなどの生体に重要なミネラルでも吸収を少なく、排泄をできるだけ多くできるように機能し、摂取過多による高ナトリウム血症や高カルシウム血症を防御しやすいシステムが基本であった。
、ところが、空気中にいる陸生動物では海水中のようにミネラルを無条件に摂取できるわけではなく、貴重な栄養素になった。陸生動物の器官も摂取することより防御が優先されて機能するのでカルシウムは腸管での吸収率が30%程度と悪く、腎臓での排泄能力が強力であるのは海生生物の系統発生的ななごりのようにみえる。
海生生物から陸生動物になる大きな内分泌学的な進化もある。魚類は血液中にカルシトニンとう血液中のカルシウムを骨に蓄えるホルモンをもっているが、陸生動物の両生類以上の脊椎動物では、魚類にはない、骨を壊してカルシウムを引き出す副甲状腺ホルモンをもつようになる。カルシウムが豊富に摂取できるときにカルシトニンによりカルシウムを骨にたっぷり蓄え、不足するときには副甲状腺ホルモンにより骨からカルシウムを必要なだけ引き出すことができるようになったわけである。
、このカルシウムを出し入れする2つのホルモンを、ビタミンDとともにその働きの通りに『カルシウム調節ホルモン』という。
空気中での重くなった体重を支える筋肉は骨の端と他の骨の端に接着し、より強力、強靱になっていく。このことは陸生動物では骨により強い圧力がかかり、骨もより堅牢になっていくとともに、大量のカルシウムの蓄積ができることになった。
5.カルシウムは骨の主成分、その意味は?
ここで骨の成分表(表3)【骨の成分とミネラル量】を見ていただきたい。
| (表3)【骨の成分とミネラル量】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
骨には種々の物質が含まれている。石灰化成分としてのカルシウムとリン酸、膠原線維であるコラーゲン、糖蛋白や酸性ムコ多糖類などの蛋白質や骨をつくるオステオカルシンという蛋白、その他脂質、マグネシウムなどのイオンを含んでいる。
、特に注目してほしいのはカルシウムの総量のうちの骨に存在する比率で、マグネシウムは50%が骨にあり、リンは88%、カルシウムは99%が骨に局在していることになる。女性のからだにはカルシウムが1.000gある。こうち990gは骨にあるが、残りのたった10gが血液などの細胞外液にあるだけである。このことはどんな意味をもつのだろうか。血液のカルシウム濃度は8.5〜10.0mg/dlの狭い範囲に保たれている。たった0.01%のわずかなカルシウム水溶液なのである。しかしこの濃度の10%くらいが低下したり上昇したりすると、筋肉のひきつれや吐き気などヒトでも症状が起こる。
、例えば血中のカルシウム濃度が6.0mg/dl以下になると全身の強直性の痙攣が起こり、いわゆるテタニー発作を生じ、12.0mg/dl以上になると意識がはっきりしなくなり、もっと上昇すると昏睡にいたる。血中のカルシウム濃度が高くても低くてもそれが長引くと生命の危機になる。
、このことから、血液中のカルシウムが8.5〜10.0mg/dlの狭い範囲に恒常状態を保つことがからだの細胞、ひいてはその個人の生命を維持していくのに必須の条件であることが理解できるだろう。ここでは血液中になくてはならないがごくわずかな0.01%濃度しか必要でなく、それ以上でも都合が悪くなるので血液から隔離して1カ所に貯蔵しておくことが大切なのである。しかし、0.0085%以下になるときには即時に血液にカルシウムを供給できなくてはならない。この難しい条件を陸生動物としてより重い体重を支えるために発達した骨組織が担っていることになる。
骨とは、陸生動物として進化していくうえで非常に合理的に発達し、必須の骨格形成の担い手であるとともに、大量のカルシウム貯蔵庫の2つの役割を果たすことになったわけである。ここに人類の骨粗鬆症という病気の宿命づけがなされている。
、カルシウム不足やなんらかのカルシウム需要が増加したとき、骨から日々大量のカルシウムが血液に供給されることになる。その陰で骨格としての骨の堅牢さは犠牲にされているわけであるから、長期のカルシウム不足状態は骨折や骨変形による内臓臓器の障害など、骨格形成にとって危機的状態となりうるわけである。6.カルシウム摂取とカルシウムバランス
(図4)【日本、米国の1日あたりのカルシウム所要量】、それでは、どのくらいのカルシウムを食べればよいのかということが問題になる。厚生省によるわが国でのカルシウム所要量は年齢にもよるが(図4)、成人で1日に600mgと設定されている。この600mgという数字は、だれでもが必要な最小限の量と理解されている。『600mgを食べればいい』というより『600mgは少なくとも食べる必要がある』という意味である。
、ちなみに米国では成人で1,000mg、閉経後や老人は1,500mgとされているのは、あくまで目標量の目安であり、この数値の意味はわが国の600mgとは若干異なるといえる。それでは、実際に食べたカルシウム量はどのくらい腸管から吸収され、骨に蓄えられるのか。このことを考えるのに『カルシウムバランス』という考え方がある。食べた量から糞便と尿に失われる量を 差し引いた量がプラスなら骨にカルシウムが蓄えられ、マイナスなら骨からカルシウムが失われたという、いわゆるからだのカルシウムの出納である。これは汗から失われるカルシウムを無視し、かだに吸収されたカルシウムは血液中に入り、骨のカルシウムと交換、取り込まれると考えているからである。
(図5)【腸管でのカルシウム吸収量と摂取量の関係】
カルシウムの摂取量と腸管で吸収された量(食べた量から糞便に排泄された量を引き算した量)を調べてみると図5のような関係がある。
、1.000mgを食べると230mgが吸収されるということになるが、これはあくまで平均的な数字であり、この図から人により個々に相当の違いがあることがわかっていただけるだろう。腸管でのカルシウム吸収量と尿への排泄量には図6のような関係がある。
(図6)
【腸管でのカルシウム吸収量と尿中排泄量】この図でみると150mgを吸収したときに150mgの尿への排泄があり、カルシウムの出納はちょうどゼロとなる。
そうすると、吸収率を150mgにするためには、図5から推測して560mgのカルシウム摂取が必要になる。
この意味は、平均的には560mgのカルシウムを食べれば便と尿への排泄と釣り合いがとれ、差し引きゼロのカルシウム・バランスになることを意味する。
このようにこれらの図を利用してカルシウム・バランスをみると表4のようになる。
(表4)【計算上のカルシウム・バランス】 カルシウム摂取量
(mg/日)腸管での吸収量
(mg/日)尿中カルシウム排泄量
(mg/日)カルシウム・バランス
(mg/日)300 80 140 -60 500 130 145 -5 560 150 150 0 600 170 160 10 800 200 175 25 1,000 230 180 50 1,500 300 200 100 バランス点は560mgで、300mgの摂取だと1日−60mg、800mgの摂取だと1日+25mgとなる。ここで不思議なことは、バランス点の560mgより250mg少ない300mgを食べたときは60mgもマイナスになるのに、240mg余分に食べてもブラスはたった25mgに過ぎないことである。一度300mgの日があったら、800mgを食べる日が2日半も必要になり、カルシウムを蓄えることは大変に困難で、不利なことだと理解してもらえるのではないだろうか。
おわりに
地球の環境で生物が生まれ、カルシウムが豊富な海水という世界で繁栄・進化してきたために、カルシウムは細胞生存のため必須のミネラルであるにもかかわらず、からだの機構としてはカルシウム過剰から防御することが主で、カルシウムを温存することに欠けていることがこのカルシウム・バランスの不利からも納得できる。だからこそ、陸上生活を営む人類にとってカルシウムを十分に食べることは生理学的にも、臨床医学的にも大変に大切なことといえるのである。